良い老人ホームの見分け方を教えます!チェックポイント16項目
素敵な老後を送るためにも、「良い」老人ホームに入りたいと考えている方は多いでしょう。しかし老人ホームの数は非常に多く、どの施設が自分に最適なのか見分けるのは至難の業です。そこでこの記事では、良い老人ホームを見分けるためにチェックしたい16項目を紹介します。老人ホームの見分け方を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

良い老人ホームとは?

そもそも「良い」老人ホームとは、どのような施設なのでしょうか。もちろん「良い」の定義は人それぞれですが、サービスが充実しており、さらに雰囲気もよく安心して生活できるなら、それは良い老人ホームであるといえるでしょう。
しかし現実的には、老人ホームにかかる費用も考慮しなければなりません。すべての希望条件を満たしていないとしても、良心的な料金体系で老後資金の心配をすることなく暮らせるとしたら、それも良い老人ホームといえるかもしれません。
また、老人ホームに入居したとしても、家族になるべく多く会いたいと思う方もいるでしょう。そのような方にとっては、家族が面会に来やすい立地にある老人ホームこそ良い施設だと考えるのではないでしょうか。
このように、「良い」老人ホームを探すためには意識すべきポイントが多々あり、トレードオフの関係になる要素も少なくありません。入居してから後悔しないように、チェックすべきポイントを漏れなく把握しておきましょう。
老人ホームの見分け方!16項目解説

それでは老人ホームを選ぶときに意識すべきポイントを16項目紹介します。
● 料金・費用
● 介護体制
● リハビリ体制
● 医療体制
● 介護スタッフ
● 職員の定着率
● 施設の設備・環境
● イベントの内容
● 入居率
● 入居者の雰囲気
● 立地条件
● 経営状況
● 緊急時の対応
● 事故に関する体制
● 相談窓口
● 事前の情報開示
それぞれの項目ごとに、「良い」老人ホームの答えは一つではありません。どのような状況の人は、どのようなポイントを意識して老人ホームを選べばいいのか、詳しく見ていきましょう。
【ポイント1】料金・費用

まず気にする方が多いのが、老人ホームにかかる料金・費用です。実は老人ホームにかかる費用は、「入居一時金」と「月額利用料」の2つに大別されます。老人ホームの種別ごとの相場は次のとおりです。
| 種類 | 入居一時金 | 月額利用料 | |
| 公的 | 特別養護老人ホーム (特養) | 0円 | 4.9~15.0万円 |
| 介護老人保健施設 (老健) | 0円 | 6.7~16.2万円 | |
| 介護医療院 | 0円 | 6.8~17.0万円 | |
| 軽費老人ホーム (ケアハウス) | 0~30.0万円 | 9.3~22.0万円 | |
| 民間 | 介護付き有料老人ホーム | 0~630万円 | 15~35.1万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0~46.0万円 | 13.4~31.5万円 | |
| 健康型有料老人ホーム | 0~1億円 | 10~40.0万円 | |
公的施設は入居一時金・月額利用料ともに低く抑えられていますが、人気も高く、入居待ちが発生していることも少なくありません。そのためスムーズに入居するためには、民間の有料老人ホームを選んだほうがいいでしょう。
民間の有料老人ホームの場合、家賃の前払い的な性質を持つ「入居一時金」が必要となります。ただし入居一時金はすべての有料老人ホームで必要となるわけではなく、入居一時金が0円の施設も少なくありません。
なお、入居一時金の一部は、入居に伴う手数料として初期償却されます。そして「初期償却率」や「入居一時金の償却期間」は施設ごとに異なるため、入居前に確認してみてください。短期で退去する場合は入居一時金の一部が返還されますが、初期償却率・償却期間によって返還額が異なるためです。
高級老人ホームなら良いホーム?
民間の有料老人ホームの場合、上記で紹介した相場よりも価格帯の高い施設も存在します。いわゆる高級老人ホームです。高級老人ホームなら「良い」施設といえるでしょうか?たしかに高級な施設はサービスが豊富で施設も整っているため、満足度が高い可能性は高いでしょう。
しかし、理想の生活スタイルによっては、高級老人ホームであるからといって「良い」施設であるとは限りません。たとえば他の入居者と交流したいと考えているにも関わらず、レクリエーション・イベントがあまり開催されない施設に入居したとしたら、退屈してしまうでしょう。たとえ高級老人ホームを選択肢としているとしても、理想の生活が送れるかどうかチェックすることが重要です。
【ポイント2】介護体制

老人ホームであるからといって、介護体制が整っているとは限りません。たとえば健康型有料老人ホームの場合、介護が必要になった方は退去しなければなりません。また、住宅型有料老人ホームも、原則として自立した高齢者を対象としています。入居後に介護の必要性が生じた場合、外部の居宅介護サービスを利用することは可能ですが、トイレ・お風呂が必ずしも介護に適した仕様であるとは限りません。もし施設内での生活に支障が生じた場合、介護サービスを提供している施設へ転居する必要があります。
このように老人ホームの介護体制によっては、入居後に意図せずして転居しなければならないケースもあるのです。現在の身体状況はもちろん、将来的な介護の必要性も視野に入れて施設を選んだほうが安心です。
【ポイント3】リハビリ体制
老人ホームの中には、体力維持・筋力低下や寝たきり予防の一環として、リハビリテーションに力を入れている施設もあります。このようなリハビリテーションを重視する方は、どのような種類のリハビリが実施されているのかはもちろん、配置されている専門家についてもチェックしてみてください。主なチェックポイントは次の4点です。
● 理学療法士が配置されているか
● 作業療法士が配置されているか
● 言語聴覚士が配置されているか
● 生活リハビリの内容はどうか
それぞれ詳しく解説します。
理学療法士が配置されているか
理学療法士(PT)はリハビリの中でも、とくに「運動機能の回復」を目的とした療法に特化した専門家です。次の2種類の療法により、低下した運動機能の回復を目指します。
| 運動療法 | 機能が低下した身体部位を正常な状態に回復するために、起き上がる・座る・立ち上がるなどの基本動作を訓練する |
| 物理療法 | 痛みを緩和したり運動機能を向上させたりするために、マッサージ・電気治療・温熱治療などを実施する |
運動機能にフォーカスしたリハビリを実施したい方は、理学療法士が配置されている老人ホームを選びましょう。
作業療法士が配置されているか
作業療法士(OT)はリハビリの中でも、とくに「日常動作の回復」に特化した専門家です。運動機能が完全に回復していない状態であっても、食事・トイレなど日常的な動作を行えるようにリハビリしてくれます。
身体に残った機能を活かし、日常生活を送りやすくしてくれる点が作業療法士の特徴です。たとえば怪我の後遺症で足が不自由な方が、杖などを使って自分の足で歩きたいと希望する場合、作業療法士を頼ることになります。作業療法士が在籍する老人ホームも多いため、ぜひ検索してみてください。
言語聴覚士が配置されているか
言語聴覚士(ST)は言語コミュニケーションや摂食・嚥下機能を改善維持するためのリハビリテーションを専門としています。「言語聴覚」という名称のとおり言語による意思疎通を訓練してくれることはもちろん、食べ物を「嚙む」「飲み込む」といった能力を改善してくれることが特徴です。
高齢になると嚥下能力が低下し、食事が難しくなることも珍しくありません。食事についての問題を抱えている方は、言語聴覚士が配置されている施設を選ぶといいでしょう。ただし、理学療法士・作業療法士と比べると、言語聴覚士が在籍している施設は多くありません。希望エリアに言語聴覚士がいる老人ホームがあるか、一度スマートシニアで検索してみてください。
生活リハビリの内容はどうか
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が実施するリハビリテーションではなく、日常生活で行う動作そのものをリハビリとして捉え、その動作を支援することを「生活リハビリ」と呼びます。たとえば着替え・食事・トイレなどの動作を自分で行えるように支援することが、生活リハビリの代表例です。日常生活をなるべく自立して送れるようにしたい方は、これら生活リハビリの体制が整った施設を選ぶことをおすすめします。
【ポイント4】医療体制

通常の介護職員であっても、次のような医療ケアは実施できます。
● 体温測定
● 目薬の点眼
● 服薬の介助
● ガーゼの交換
● 湿布の貼付
また、特定の研修を終えた介護福祉士は、「口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引」「胃ろうなどによる経管栄養」などの医療行為にも対応可能です。しかし、これら一部の医療ケアを除き、介護職員は原則として医療行為を行えません。つまり老人ホームでインスリン注射・点滴管理などの医療行為を受けるためには、看護師が在籍している施設を選ぶ必要があるのです。
なお、介護老人保健施設(老健)には医師・看護師・介護職員が常駐しています。一方で特別養護老人ホーム(特養)の場合、常駐しているのは看護師・介護職員のみで、医師は非常勤です。民間の有料老人ホームの場合、介護職員は常駐している施設が多いものの、看護師が在籍しているかどうかは施設によって異なります。(基本的に医師は在籍していません)老人ホームを選ぶときは、入居後に必要となる医療行為に対応してもらえるかどうかもチェックしてみてください。
【ポイント5】介護スタッフ

老人ホームで気持ちよく生活できるかどうかは、介護スタッフが丁寧に対応してくれるかどうかによっても左右されます。ホームページやパンフレットからだけでは介護スタッフの良し悪しを確認できないため、ぜひ体験入居でチェックしてみてください。
体験入居すると、他の入居者と同じようにサービスを受けられます。体験入居でスタッフの人当たりを確認し、もっとも相性がいいと感じた施設を選ぶといいでしょう。なお、体験入居できる期間は1日〜1週間程度で、費用は1泊5,000〜15,000円程度の施設が多いです。また、体験入居中に受けた介護サービス費は介護保険適用外となり、全額自己負担となることは覚えておきましょう。
【ポイント6】職員の定着率
一般的に「良い」会社は社員の定着率が高いといわれています。これは老人ホームも同様です。職員の定着率が高い施設はそれだけ働く人を大切にしており、結果として入居者が受けるサービスも充実していることが多いでしょう。
職員の状況については各老人ホームごとの「重要事項説明書」に記載されているため、ぜひ確認してみてください。「重要事項説明書」とは介護施設が作成・都道府県に提出する義務のある書類のことで、入居者にも契約前に提示されます。契約時ではなく、施設見学などの際にもらうことも可能です。入居先施設を選んでいる段階でそれぞれの施設から重要事項説明書を取り寄せ、それぞれの施設ごとに職員の状況を比較してみるといいでしょう。
【ポイント7】施設の設備・環境
老人ホームは基本的にバリアフリーの構造であるものの、必ずしも介護に対応しているとは限りません。たとえば手すりやスロープは、ほとんどの施設で充実しているでしょう。しかし住宅型有料老人ホームなど自立した高齢者の受入を前提としている施設の場合、廊下や共有スペースが車椅子に対応しているとは限りません。
また、お風呂にも手すりは設置されているケースが多いですが、自立した方の入浴を前提としている施設も多いです。一人での入浴(自力での入浴)が難しい場合は、機械浴の設備が整った老人ホームを選ばなければなりません。入居後の生活に苦労しないためにも、老人ホーム選びの際は身体状況を考慮してください。
また、個室の設備を選んだとしても、トイレ・お風呂が居室ごとに設置されているとも限りません。これらの水回り設備が共有スペースのみに設置されている老人ホームもあります。もしプライベートを確保して暮らしたいと考えている場合は、居室の設備にも注意してください。
【ポイント8】イベントの内容

多くの老人ホームでは、クリスマス会などの年中行事(イベント)や、入居者同士のレクリエーションが開催されています。このイベント・レクリエーションの内容は施設によって大きく異なるため、入居者の好みにあっているかどうか必ず確認しましょう。
たとえば、地域の人と交流したり少し外に出て食事したりといったアウトドア系のイベントが多い施設もあります。一方、音楽鑑賞・映画鑑賞などインドア系のイベントをメインとした施設も少なくありません。
入居者が人との交流・外出が好きなら、アクティブなイベントの多い老人ホームを選んだほうが楽しめるでしょう。一方、あまり外に出たくないという方なら、落ち着いたイベントが多い老人ホームを選ぶべきです。老後生活を楽しむためにも、好みに合うイベントが開催されているかどうか確認してみてください。
【ポイント9】入居率
老人ホームの入居率も、施設選びで重視すべきポイントの一つです。長期にわたって安心して暮らすためには、経営が安定した施設を選ばなければなりません。入居率が高い施設はそれだけ収益基盤がしっかりしており、経営が立ち行かなくなる可能性も低いでしょう。開設したばかりの老人ホームの入居率は低い傾向にありますが、開設から数年経っているにも関わらず入居率が50%に満たない施設には注意してください。
また、入居率が著しく低い施設は、設備やスタッフに問題があり、退去が多く発生している可能性もあります。安心して暮らせる施設かどうか確認するために、入居者の主な退去理由を聞いてみてもいいでしょう。なお、入居率や入居者の人数、属性退去者などの情報も、先述した「重要事項説明書」で確認できます。
【ポイント10】入居者の雰囲気
主観的な判断ポイントですが、入居者の雰囲気についても意識してみてください。入居者の雰囲気が明るいなら、総合的に「良い」老人ホームである可能性が高いです。雰囲気を肌で感じるためにも、ぜひ体験入居を申し込んでみてください。
一方、入居者の雰囲気が暗い場合、何らかの問題を抱えている可能性があります。スタッフの対応が悪かったり、レクリエーション・イベントがつまらなかったり、考えられる原因はさまざまですが、体験入居時の直感を信じて入居是非を判断してもいいでしょう。
なお、体験入居ではなく見学に行く場合は、11時30分くらいから施設を訪れてみてください。この時間に訪問すると、食事風景を見学できるためです。入居者が楽しそうな雰囲気で食事をしていれば、「良い」老人ホームであると考えられます。
【ポイント11】立地条件

「良い」老人ホームを選ぶためには、施設の立地条件にも配慮したほうがいいでしょう。これまでの住宅と近い施設なら環境変化が少なく、入居に伴うストレスを軽減できます。たとえ離れた場所の施設に入るとしても、これまで暮らしていた地域と似た環境のほうがストレスを感じづらくおすすめです。(たとえば静かなエリアで暮らしていた方が、急に都市部の施設に移ると、外出を控えてしまうかもしれません)
また、入居者本人の希望だけではなく、家族が面会に行きやすい場所かどうかも意識してみてください。家族がアクセスしやすいエリアの老人ホームなら、日ごろから面会しやすいことはもちろん、万が一の場合にもすぐに駆けつけられるため安心です。

関連記事
老人ホームの希望条件①立地条件のポイント
【ポイント12】経営状況
入居率の項目で少し触れましたが、安心して長く暮らし続けるためには、老人ホーム運営母体の経営状況も意識したほうがいいでしょう。施設の収益性の観点から考えると、やはり入居率が高い施設がおすすめです。
また、民間の老人ホームに入居する場合、運営母体の信用性も確認したほうがいいでしょう。老人ホームの運営母体は医療法人・地域の中堅企業・上場企業などさまざまです。運営母体の経営基盤がしっかりしていれば、老人ホームの入居率が多少低いとしても、施設が倒産してしまう可能性は低いでしょう。施設のホームページなどで、運営母体の情報を探してみてください。
【ポイント13】緊急時の対応
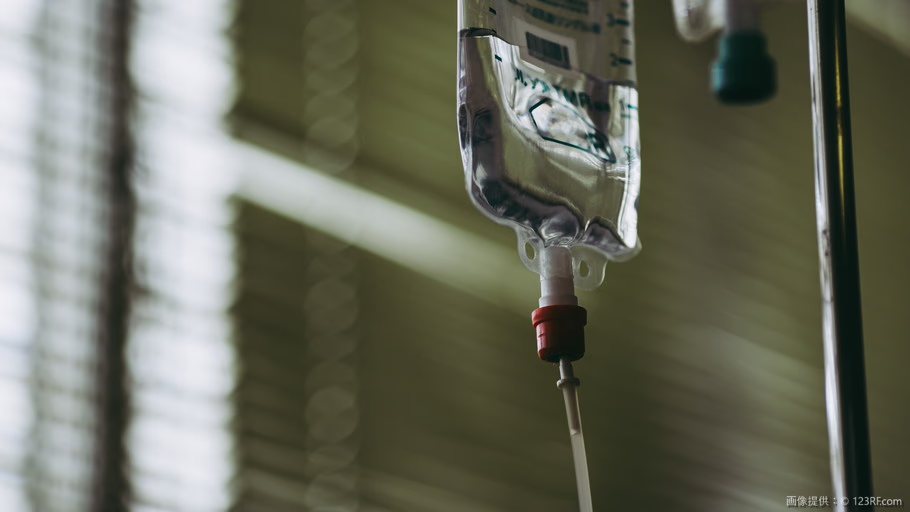
万が一の場合を考えると、緊急時の対応が充実した施設を選んだほうが入居者・家族ともに安心できます。とくに次の3つのケースについて、どのような体制が敷かれているのか確認してみてください。
● 入居者の容体が急変した時
● 夜間に緊急事態が発生したとき
● 災害が発生したとき
それぞれ詳しく紹介します。
急変時の対応
何らかの持病がある場合、体調が急変した場合の対応については確認しておくべきです。たとえば多くの老人ホームには、夜間の看護師常駐が義務付けられていません。しかし中には、施設の運営方針として看護師(医療関係者)を24時間常駐させている施設もあります。
もし急変に備えたい場合は、看護師が常駐している老人ホームを探してみてください。医療機関が運営する老人ホームは、看護師などが常駐しているケースが多いです。なお、施設に医療関係者が常駐していないとしても、訪問看護ステーションと契約している老人ホームなら、容体急変時にもスピーディーに対応してもらえます。
夜間の対応
ほとんどの老人ホームは、日中より夜間のほうが人員が少なくなります。たとえ日中はスタッフが充実しているとしても、夜間は人手不足になっている可能性があるため注意してください。もし体調などに不安がある場合は、夜間も定期的な巡回を実施している老人ホームを選ぶといいでしょう。
なお、巡回の頻度は施設によって異なりますが、おおむね1~2時間ごとに巡回している施設が多いです。入居者の状態によって異なるため、もし頻繁に巡回してもらいたい場合には、夜間でも人手に余裕がある施設を選ぶといいでしょう。
災害時の対応
災害時の対応についても、必ず確認しておきましょう。たとえば老人ホームは入居者が高齢者ばかりであるため、洪水・津波などから避難するにも時間がかかります。もしハザードマップ上で浸水想定エリアにある施設を選ぶ場合は、災害時の避難体制を確認してから入居を決めたほうがいいでしょう。
たとえば垂直避難(2階以上の安全な場所へ避難する方法)の訓練が実施されている施設なら、予期せぬ水害が発生しても比較的安心できます。もし足が不自由な方が入居する場合は、停電でエレベーターが使えなくなった場合の避難方法などについても確認してみてください。
【ポイント14】事故に関する体制
老人ホーム内で事故に遭遇してしまった場合の体制についても確認しておくべきでしょう。事故を防ぐ体制も重要ですが、事故発生時の対応も整備されている施設のほうが「良い」老人ホームである可能性が高いためです。主なチェックポイントは次の2点です。
● 賠償事故が発生したときの対応
● 第三者による評価の実施状況
それぞれ詳しく解説します。
賠償事故が発生したときの対応
各老人ホームごとの「重要事項説明書」には、事故予防への取り組み内容はもちろん、施設が提供したサービスによって賠償事故が発生したときの対応についても記載されています。また、老人ホームとして損害賠償責任保険に加入しているかどうかも確認可能です。これらすべての情報が網羅的に記載されている施設なら、万が一の場合にも誠実に対応してもらえる可能性が高いです。
第三者による評価の実施状況
「重要事項説明書」には、施設の提供サービスについて「第三者による評価」が実施されているかどうかも記載されています。第三者による評価が定期的に実施されている施設は、それだけ提供サービスの品質を改善しようとしていると考えられるでしょう。このような姿勢が見られる施設は、事故が発生する可能性も比較的低いことがポイントです。
また第三者による評価だけではなく、入居者へのアンケート調査が実施されているかどうかも確認してみてください。アンケート結果がサービス内容に反映されている施設は、入居者のことを考えている「良い」老人ホームだといえるでしょう。
【ポイント15】相談窓口
「重要事項説明書」には事故・苦情発生時の対応窓口・連絡先・受付時間なども記載されているため、あわせて確認しておきましょう。入居者はもちろん家族からの相談も受け付けている施設は、それだけ誠実な老人ホームだといえます。
入居前の打ち合わせで、これまでにどのような相談が持ち込まれたことがあるか聞いてみてもいいでしょう。その相談内容・対応方法から、安心して入居できる施設なのかどうか判断できます。
【ポイント16】事前の情報開示
入居希望者に対して事前にどれだけの情報を、どのように開示してくれるのかも、「良い」老人ホームを見分けるためのポイントです。たとえば経営状況が安定している老人ホームかどうかチェックするために、事業収支計画書・財務諸表などを閲覧したいと考える方もいるでしょう。
令和6年度からはすべての介護事業所に財務諸表の都道府県知事への報告・公表が義務付けられていますが、損益計算書(PL)・貸借対照表(BS)・資金収支計算書(CF)がしっかりと開示されているかどうか確認してみてください。
また、ここまで何度か触れている「重要事項説明書」をどのタイミングで開示してくれるかも、「良い」老人ホームかどうか判断するためのポイントです。契約直前にしか開示してくれない施設より、検討段階の見学時から開示してくれる施設のほうが、運営状況の透明性が高く安心できるでしょう。
契約前に「重要事項説明書」をチェックしよう
ここまで「良い」老人ホームを見分けるための16個のポイントを紹介してきましたが、その多くは「重要事項説明書」に記載されています。そして繰り返しとなりますが、「重要事項説明書」は契約直前ではなく、施設見学などのタイミングでもらうことも可能です。
いくつかの老人ホームを比較している段階からそれぞれ「重要事項説明書」を取り寄せ、この記事で紹介した各ポイントを比較してみてください。施設ごとにポイントを細かく確認することで、施設の良し悪しが見えてくることもあります。(昨今では多くの老人ホームが、ホームページに重要事項説明書のPDFをアップしています)
なお、「重要事項説明書」をチェックするときは、それが最新の内容であるかどうかも確認しましょう。記入年月日が1年以内なら最新の内容である可能性が高いですが、数年前の日付になっている場合、念のため施設側に確認してみてください。
老人ホーム探しは重要視するポイントを定めてから
長期間にわたって暮らすことになる老人ホームを探すからには、可能な限り「良い」老人ホームを探したいと考える方も多いでしょう。しかし現実的に考えると、ここまで紹介した各ポイントのすべてが優れた老人ホームは存在しません。たとえば立地がいい施設は、費用が高い可能性が高いです。立地に優れているにも関わらず費用が安い施設は、スタッフ数が少なくサービスの質が低い可能性もあるでしょう。
トレードオフの関係になっているポイントも多いため、「良い」老人ホームを見つけるためには、重視したいポイントに優先順位をつけることが大切です。この記事で紹介した16個のポイントを「絶対にこだわりたいポイント」「できればこだわりたいポイント」「それほど重視しないポイント」などに分類してみてください。
老人ホームの見学時のポイント
「良い」老人ホームを見極めるポイントを理解したとしても、やはりパンフレット・ホームページなどだけで見極めることは難しいでしょう。インターネットなどで情報収集し、候補先をいくつか絞ったら、本当に「良い」老人ホームであるかどうか確認するためにも一度見学に行ってみてください。
見学時には建物・設備の状況がパンフレットと相違がないか、スタッフや入居者の雰囲気が明るいかなど、現地でしかわからないポイントをチェックしてみてください。施設によっては、普段提供されている食事を試食できることもあります。記事前半で触れたとおり、11時30分くらいから施設を訪れ、試食と併せて入居者の食事風景を確認するのもおすすめです。
また、パンフレット・ホームページを見て疑問に感じたことは、リストアップしておき、漏れなく質問することをおすすめします。老人ホームを見学する際のポイントは次の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
「良い」老人ホーム・介護施設の定義は人それぞれです。そして「良い」老人ホームを見分ける方法は、一つだけではなく、次のように多岐にわたります。
● 料金・費用
● 介護体制
● リハビリ体制
● 医療体制
● 介護スタッフ
● 職員の定着率
● 施設の設備・環境
● イベントの内容
● 入居率
● 入居者の雰囲気
● 立地条件
● 経営状況
● 緊急時の対応
● 事故に関する体制
● 相談窓口
● 事前の情報開示
これらすべてのポイントに優れた施設を見つけることは簡単ではなく、優れたポイントが多ければ多いほど費用が高くなってしまう可能性も高いです。なるべくスムーズに理想的な老人ホームへ入居するためにも、各項目に優先順位をつけ、優先度の高いポイントを条件に老人ホームを検索してみてください。
スマートシニアではエリアや費用・施設種別・介護度・入居条件はもちろん、専門スタッフの常駐体制や夜間対応、医療・看護体制、「居室にトイレがあるか」「海が見えるか」などのこだわり条件を選択することで、効率的に理想の老人ホームを探せます。自分にとっての「良い」老人ホームを探したい方は、ぜひスマートシニアで検索してみてください。
この記事を読んだ方によく読まれています

老人ホームの入居条件は?年齢・介護度・認知症の有無、医療依存度など
2025.06.20

高級老人ホームの需要とは?どのような人におすすめか解説!
2024.10.05

高級老人ホームの実態は?失敗事例や失敗しないためのポイントを解説
2025.06.21

自立型老人ホームとは?費用や入居するメリット・デメリットを紹介
2025.06.21






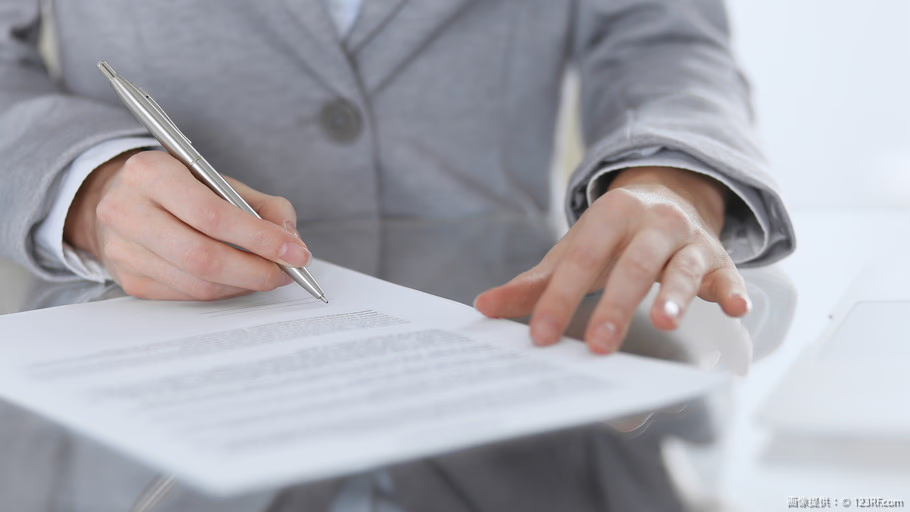





有料老人ホームで介護士として約12年勤務した後、社会福祉士を取得。急性期病院の医療ソーシャルワーカーとして、入退院支援に携わる。現在は、スマートシニア入居相談室の主任相談員として、多数のご相談に応じている。