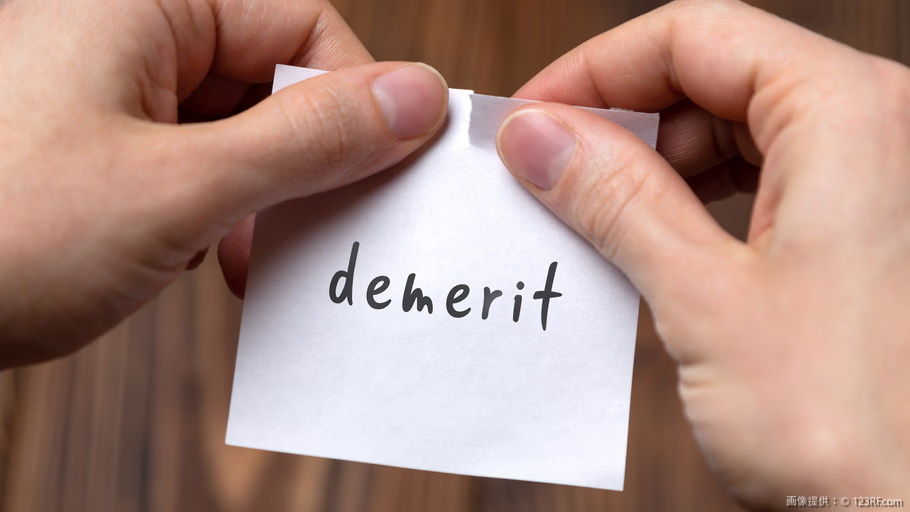シニア向け分譲マンションとは?特徴や購入におけるデメリット・注意点を解説
介護施設ではない高齢者向け施設として、シニア向け分譲マンション(高齢者用マンション・シニアマンション)への注目が高まっています。制約が少なく自由に生活できることはもちろん、あくまでも分譲物件であるため次世代に資産として残せることがメリットです。そこで今回は、シニア向け分譲マンションの特徴や、購入におけるデメリット・注意点についても解説します。シニア向け分譲マンションの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

渡口 将生
シニア向け分譲マンションとは?
シニア向け分譲マンションとは、高齢者が過ごしやすいように、バリアフリー設備が充実しているマンションのことです。販売価格・毎月の管理費が高額であるため、富裕層向けのマンションであるともいえます。あくまでも介護施設ではなく、高齢者のための分譲マンションであるため、介護サービスなどは提供されていません。ただし病院やクリニックなどが併設されているケースも多く、万が一の場合に備えたい高齢の方でも安心して暮らすことができます。
また、シニア向け分譲マンションは一般的に用いられている名称で、法律上はあくまでも通常の「分譲マンション」です。そのため子や孫に相続・贈与することはもちろん、他の高齢者に転売することもできます。
シニア向け分譲マンションの特徴
シニア向け分譲マンションの特徴としては、次のような点が挙げられます。
● 自由な生活ができる
● 他の高齢者施設に比べて居室が広い
● 所有権があり売却も可能
● 資産価値にもなり相続ができる
● ライフサポートや共有設備が充実している
他の高齢者施設と比べると、そのメリットは多岐にわたります。これらの特徴に魅力を感じる方は、ぜひシニア向け分譲マンションの購入を検討してみてください。それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
自由な生活ができる
シニア向け分譲マンションは介護施設ではなく、あくまで「住まい」として提供されています。そのため介護施設のような行動制限はなく、外出や外泊も自由です。また、友人や家族を招くことも可能で、日常生活を自分のペースで自由に楽しむことができます。
もし将来的に介護やサポートが必要になった場合も、その必要性が軽微な場合は、外部事業者の訪問介護サービスを導入することも可能です。このように自宅と変わらず自由に生活できることが、シニア向け分譲マンションの最大のメリットといえるでしょう。
他の高齢者施設に比べて居室が広い
一般的な高齢者施設と比べると、シニア向け分譲マンションは居室が広めに設計されています。たとえば、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームの居室の最低面積は13㎡(約8.5畳)です。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の居室の最低面積は25㎡(約16畳)、キッチンや浴室などを共同利用する場合は18㎡(約11.5畳)とされています。
一方、シニア向け分譲マンションには明確な最低面積基準がありませんが、35〜100㎡(19〜54畳)以上で設計されているケースが多いです。リビングやダイニングなどもあり、広々とした空間で生活できることも大きなメリットといえるでしょう。
所有権があり売却も可能
有料老人ホームなどは利用権を契約する形態、サービス付き高齢者向け住宅は賃借権を契約する形態であるのに対し、シニア向け分譲マンションは所有権を購入する形態です。そのため一般的な分譲マンションと同じく、部屋を売却することもできます。
たとえば元気なうちにシニア向け分譲マンションに入居し、介護の必要性が高くなったら介護付き有料老人ホームへ転居するケースも珍しくありません。この場合、シニア向け分譲マンションの売却費用を、有料老人ホームの入居資金として活用することも可能です。このように財テクの手段となることも、シニア向け分譲マンションならではのメリットといえるでしょう。
資産価値にもなり相続ができる
シニア向け分譲マンションは他の高齢者に賃貸物件として貸すことができます。そのため資産価値が生まれやすいことも特徴です。また、他の所有不動産と同様に、相続の対象となります。たとえば亡くなるまでシニア向け分譲マンションで暮らし、相続後は第三者に貸し出せば、相続人の暮らしを助ける効果も期待できるでしょう。
このような効果も鑑みると、シニア向け分譲マンションに入居後、介護の必要性が高くなったために介護付き有料老人ホームへ転居するとしても、あえて売却せずに物件を所有し続ける選択肢も考えられます。介護付き有料老人ホームに転居したタイミングで誰かに貸し出し、賃貸収入を介護費用に充当することも可能です。
ライフサポートや共有設備が充実している
多くのシニア向け分譲マンションでは、高齢者の暮らしを支える「ライフサポート」に注力しています。たとえば安否確認・コンシェルジュによる生活相談・緊急対応などが代表例です。施設によっては食事サービスを提供していることもあります。
また、共有設備としてレストラン・大浴場・フィットネス・談話室・ゲストルームなどを完備している施設も少なくありません。このように、日々の暮らしを彩るサービス・設備が豊富なことも、シニア向け分譲マンションならではの特徴です。
シニア向け分譲マンションの入居条件
シニア向け分譲マンションの入居条件としては、次のような項目が挙げられます。
| 入居条件 | 概要 |
| 自立していること | 日常生活動作(食事・排泄・入浴・移動など)を自分で行えることが前提 |
| 年齢 | 45~55歳以上などの制限を設けている施設もある |
| 健康状態 | 感染症・認知症の有無で入居を断られることもある |
| 資産状況 | 購入費用・管理費などを無理なく支払えるかどうか |
| 身元引受人 (保証人) | 施設により詳細条件は異なる |
前提として、シニア向け分譲マンションには自立している方しか入居できません。ここでいう「自立」とは、日常生活動作(食事・排泄・入浴・移動など)を自分で行えることを指します。要支援・要介護1など介護の必要性が低い方なら入居できる可能性もありますが、施設として介護サービスが提供されるわけではないため、外部の介護事業者と個別に居宅サービスの利用契約を結ばなければなりません。
また、年齢については、とくに制限を設けていない施設も多いです。シニア向けのサービスが提供されているものの、購入すれば誰でも居住できます。ただし一部の施設では、45〜55歳以上などの制限を設けていることもあるため注意してください。
くわえて、健康状態についての審査も行われます。感染症・認知症の有無によっては入居を断られることもあるため、あらかじめ条件を確認しておきましょう。さらに購入費用・管理費などを無理なく支払えるかどうか、資産状況を確認されることもあります。身元引受人(保証人)については施設によって詳細条件が異なるため、申し込み前に確認しておくことが重要です。
シニア向け分譲マンションで受けられるサービス
ここまでも少し触れたものも含め、シニア向け分譲マンションで受けられるサービスとしては次のような例が挙げられます。
● 見守りサービス(安否確認など)
● フロントサービス(来客対応・宅配便の取次など)
● 緊急時の対応(救急車やタクシーの手配など)
● 生活支援サポート(クリーニングの手配など)
● 食事の提供(レストランが併設されている場合)
このようなサービスが提供されるため、自宅や一般的なマンションと比べると、高齢者だけでも安心して暮らしやすいことが特徴です。なお、見守りサービス・フロントサービス・緊急時の対応は通常の管理費内で対応してもらえるケースが多いですが、生活支援サポートや食事提供についてはオプションとして別途費用がかかることも覚えておきましょう。(オプションサービスを利用した場合、翌月の管理費にオプション費用が上乗せされます)
シニア向け分譲マンションで受けられないサービス
シニア向け分譲マンションではさまざまなサービスが提供されていますが、次のようなサービスは提供されていません。
● 介護サービス
● 医療サービス
もし食事・入浴・排泄などをサポートする身体介護を受けたい場合、入居者が個別に居宅サービス事業者と契約する必要があります。ただしシニア向け分譲マンションは自立した高齢者を対象としており、バリアフリーであるものの、必ずしも介護に適した設計がされているわけではありません。そのため介護レベルが高い場合、居宅サービスを受けたとしても暮らし続けることは難しいでしょう。
もし本格的に介護サービスを受けたい場合は、シニア向け分譲マンションではなく「介護付き有料老人ホーム」への入居を検討してみてください。介護付き有料老人ホームなら介護スタッフが常駐しており、中には医療サービスを提供している施設もあります。シニア向け分譲マンション並みに豪華な設備を整えている介護付き有料老人ホームも存在するため、ぜひ一度検索してみてください。
シニア向け分譲マンションの主な設備
さて、シニア向け分譲マンションの居室にある設備としては、次のような例が挙げられます。
● リビング
● ダイニング
● キッチン
● 洗面化粧台
● トイレ
● 浴室
水回り設備については、他の高齢者向け施設では共用設備しかないこともありますが、シニア向け分譲マンションの場合は各居室ごと備えつけられています。そのためプライバシーを確保しやすいことが特徴です。また、共用の娯楽設備としては次のような例が挙げられます。
● 温泉・プール
● フィットネスジム
● カラオケルーム
● レストラン・カフェ
● 図書室
● シアタールーム
● 大浴場
さらに理美容室・ 医務室・ドラッグストア・コンビニなどが併設されている施設もあり、マンション内だけで用事を完結できることが特徴です。
シニア向け分譲マンションの価格相場
シニア向け分譲マンションで暮らすために必要な費用の相場は次のとおりです。
| 入居に必要な費用 (購入費用) | 月額費用 (管理費など) |
| 2,300~4,350万円 | 10.0~29.2万円 |
中古の物件なら、相場より安価に購入することもできます。また、月額費用は共用設備の充実度・提供サービスなどによって変動するため、いくつか気になる施設を比べてみてください。
シニア向け分譲マンションのデメリット・注意点
シニア向け分譲マンションに入居するメリットは多岐にわたりますが、少なからずデメリット・注意点も存在します。とくに留意しておくべきポイントは次のとおりです。
● 他の高齢者施設と比べて費用が高額
● 医療ケアは提供されないタイプが多い
● 売却がすぐにできない可能性もある
● 過剰なサービスが付いている場合もある
それぞれのデメリットについて、対処方法とあわせて見ていきましょう。
他の高齢者施設と比べて費用が高額
シニア向け分譲マンションにはさまざまなサービスが付帯しており、設備も豪華なため、他の高齢者施設と比べると費用が高額です。一般的な分譲マンションと比べても購入価格・ランニングコストが高いため、この点はデメリットといえるでしょう。
入居してからランニングコストの支払いに困らないようにするためには、あらかじめ予算計画をシミュレーションしておくことが重要です。ローンを使うかどうかを含め、一度プロに相談してみてもいいでしょう。
医療ケアは提供されないタイプが多い
シニア向け分譲マンションでは基本的に、介護サービスだけではなく医療ケアも提供されません。もし自立して生活できるものの健康状態に不安がある場合には、なるべく医療機関へアクセスしやすい物件を選んだほうがいいでしょう。
また、たとえクリニックが併設されているとしても、通院するたびに自分で費用を支払う必要があります。そのため予算計画をシミュレーションするときは、マンションの管理費以外に、毎月かかる医療費も想定しておくことが重要です。
売却がすぐにできない可能性もある
一般的な分譲マンションと比べ、シニア向け分譲マンションの流通市場は未成熟です。また、シニア向け分譲マンションを購入できるだけの資金を有した高齢者は、それほど多くありません。そのため売却したいと思っても、すぐに買い手が見つからない可能性もあります。
将来的な売却を見据える場合は、なるべく流動性の高いエリア(買い手需要の多いエリア)の物件を選ぶといいでしょう。都市部のシニア向け分譲マンションなら、高齢者以外の買い手が現れる可能性もあります。
過剰なサービスが付いている場合もある
サービスメニューが豊富なことはシニア向け分譲マンションの魅力の一つですが、利用頻度が少ないサービスが付いているケースも多いです。たとえば入居した直後はフィットネスジムを使うかもしれませんが、歳を重ねるごとに利用頻度が減るかもしれません。大浴場のある物件も魅力的ですが、やはり居室のお風呂に入る回数のほうが多いでしょう。
サービスメニューが多い物件を選びたくなる気持ちも自然なものですが、付帯するサービスが多ければ多いほど、ランニングコストも高くなります。そのため費用対効果の高い物件を購入するためには、事前に必要なサービスを見極める必要があるのです。
シニア向け分譲マンションの選び方
さて、シニア向け分譲マンションを選ぶときに注目すべきポイントとしては、次の3点が挙げられます。
● 立地・周辺環境の充実さで選ぶ
● 必要なサービス内容で選ぶ
● 将来のライフプランを考慮して選ぶ
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
立地・周辺環境の充実さで選ぶ
立地や周辺環境は、暮らしやすさを大きく左右します。また、立地のいい物件や周辺環境の充実した物件のほうが、資産価値が向上しやすいこともポイントです。これらの観点を加味し、次のような条件を満たした物件を選んでみてください。
● 徒歩圏内に生活に必要な施設が一通り揃っているか
● 病院やクリニックが近くにあるか(併設されているか)
● 公共交通機関にアクセスしやすいか
● 災害リスクはないか
とくに自身の身を守るためにも、災害リスクの有無は必ず確認しましょう。自治体の公表しているハザードマップをチェックし、洪水や津波の危険性がないか確認してみてください。(災害リスクの低い物件のほうが、売却もしやすいです)
必要なサービス内容で選ぶ
各物件ごとに、提供されているサービス内容はさまざまです。そのため自分のライフスタイルや趣味嗜好に応じて、本当に必要なサービスが備わっているかどうかも確認しましょう。たとえば料理が面倒な場合、食事サービスを提供している物件を選ぶ必要があります。一方、料理が好きな方なら、食事サービスはない代わりにランニングコストが安い物件を選んでもいいでしょう。
将来のライフプランを考慮して選ぶ
将来のライフプランを考慮して物件を選ぶことも非常に重要です。たとえば介護が必要になったら物件を売却し、介護付き有料老人ホームなどへ転居する予定なら、売却が容易な物件を選ぶべきでしょう。一方、物件は保有し続けて相続させる予定なら、賃貸需要のあるエリアの物件を購入したほうが相続人のメリットが大きくなります。入居中の暮らしやすさとあわせて、物件の出口戦略も考えてみてください。
シニア向け分譲マンションと他の高齢者施設との違い
シニア向け分譲マンション以外にも、さまざまな高齢者施設が存在します。それら施設とシニア向け分譲マンションは、どのような点が違うのでしょうか。ここからはとくに代表的な施設である「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」との違いについて解説します。
サービス付き高齢者向け住宅との違い
サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)は、安否確認・生活相談などのサービスが付いた高齢者向けの賃貸住宅です。自立した高齢者を対象としていることはシニア向け分譲マンションと同じですが、サ高住はあくまでも賃貸住宅であるため、数千万円に及ぶ購入費用を支払う必要はありません。入居一時金の相場は0〜22.1万円、月額費用の相場は11.3〜23.9万円程度であるため、サ高住のほうが比較的簡単に入居できることはメリットです。
また、サ高住の賃貸契約は、本人が亡くなると終了します。そのため相続人が物件を管理する必要はありません。介護施設よりは自由に暮らしたいものの、なるべく出費は抑えたいという場合には、サ高住を選んでみてください。
有料老人ホームとの違い
有料老人ホームには、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3種類が存在します。それぞれの特徴は次のとおりです。
| 比較項目 | 介護付き | 住宅型 | 健康型 |
| 対象 | 自立型:自立した方 介護専用型:要介護1~5の方 混合型:自立~要介護5の方 | 自立~要介護5の方 | 自立した方 |
| 入居時費用 | 0~630万円 | 0~46.0万円 | 0~1億円 |
| 月額費用 | 15.0~35.1万円 | 13.4~31.5万円 | 10~40.0万円 |
| 特徴 | 生活支援から身体介護、レクリエーションまで幅広く対応 | 食事や洗濯などのサービスを提供する高齢者施設 介護サービスは提供していない 居宅介護支援事業所と契約し、居宅サービスを受けることは可能 | 自立している方のみが対象 介護の必要性が高くなると退去する必要がある |
有料老人ホームはいずれも「利用権」を契約する施設であるため、「所有権」を購入するシニア向け分譲マンションとは契約形態が大きく異なります。また、介護付き有料老人ホームは施設として介護サービスを提供していることが特徴です。
また、住宅型有料老人ホームと健康型有料老人ホームでは介護サービスは提供されないものの、レクリエーションやイベントなど入居者の心身状態を保つ活動が実施されています。一方、シニア向け分譲マンションではこのような活動はありません。
シニア向け分譲マンションに住むまでの流れ
シニア向け分譲マンションに住むまでの流れは、おおむね次のとおりです。
- 希望に合う物件を探す
- 物件を扱っている不動産会社に問い合わせる
- 内覧・見学に行く
- 入居を申し込む
- 必要書類を集める
- 面談・審査を受ける
- 売買契約をする
- 入居する
まずは希望するエリアや予算、サービス内容などの条件を洗い出し、インターネットなどで物件を探します。(スマートシニアでも検索可能です)希望に合う施設をいくつか見繕ったら、物件を扱っている不動産会社に問い合わせ、詳しい情報を聞いてみましょう。さらに候補を絞ったら、いくつかの物件に内覧・見学に行ってみてください。
現地での様子に問題がなく、入居を希望する場合は、契約を申し込みます。ただし申し込んだからといって、必ずしも入居できるとは限りません。健康状態・経済状況などの審査を受ける必要があるため、健康診断書などの必要書類を集めましょう。面談・審査の結果に問題がなければ売買契約を締結し、引き渡しを受けたら入居します。
シニア向け分譲マンションを検討している人におすすめの高齢者施設
シニア向け分譲マンションを検討しているものの、希望に合う施設がなかなか見つからないという方もいるかもしれません。そのような場合は、次のいずれかの施設も選択肢に含めてみてください。
● サービス付き高齢者向け住宅
● 住宅型有料老人ホーム
それぞれの特徴や、なぜシニア向け分譲マンションの代替案となるのか、詳しく紹介します。
その1:サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は先述したとおりバリアフリー設計の賃貸住宅で、安否確認や生活相談などの支援サービスが付いています。提供されているサービスそのものはシニア向け分譲マンションと似ており、物件を購入するのか賃貸するのかといったこと以外に大きな違いはありません。生活の自由度も高いため、自立した暮らしを大切にしたい人にはおすすめです。
また、分譲マンションと比べると入居費用が抑えられるため、経済的な負担が少ないこともサ高住を選ぶメリットだといえるでしょう。物件を所有することにこだわらず、受けられるサービスを重視する場合は、ぜひサ高住も選択肢に含めてみてください。
その2:住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、介護サービスが付帯していないタイプの有料老人ホームです。高級志向の施設で提供されているサービス・設備はシニア向け分譲マンションと似ています。施設の数も多く、選択肢が多いことはメリットです。
また、住宅型有料老人ホームも自立した高齢者を対象としているものの、介護レベルが高くなっても居宅サービスを使えば暮らし続けられる施設もあります。そのため、同じ施設に暮らし続けたいと考えている方にとってはおすすめです。ただし老人ホームであるため、シニア向け分譲マンションやサ高住と比べると、自由な外出・外泊は難しいでしょう。
まとめ
シニア向け分譲マンションは富裕層を対象としているためサービス・設備が非常に充実しており、資産価値も高いことが特徴です。資産に余裕があり、老後の生活を豊かに過ごしたいと考えている方にとっては最適な選択肢といえるでしょう。
ただし介護サービスは付帯しておらず、介護を前提とした設計がされていないため、介護レベルが高くなると退去する必要があります。そのため長期的な目線を持って物件を選ぶことが重要です。また、シニア向け分譲マンションの供給量は限られています。もし自宅での暮らしに不安を感じており、早めに高齢者向けの施設へ引越したい場合には、似たサービスが受けられるサービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームも選択肢に含めながら物件探しを進めることが重要です。
スマートシニアでは、シニア向け分譲マンション・サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームのすべてを検索できるため、ぜひ物件探しに活用してみてください。
この記事を読んだ方によく読まれています

特養(特別養護老人ホーム)の3つの種類について|それぞれの特徴や入居条件から、申し込みできる施設を知ろう
2025.01.23

高級老人ホームとは?特徴や一般的な老人ホームとの違いを徹底解説
2025.04.02

高級老人ホームの問題点はあるのか?入居前に抑えておくべきポイントを解説!
2025.04.28

生活保護者がグループホームに入れる?向いてる人の特徴を解説
2024.09.01